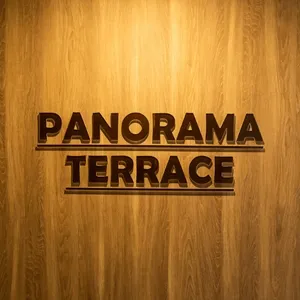星空新着情報 Starry News
【2025年】1月の天文現象
- 投稿日
- 2024.12.31
- カテゴリー
- 星空情報
.jpg)
夕方、月が金星と土星に相次いで接近
夕方の南西の空には、宵の明星とも呼ばれる金星と、それよりもやや暗いものの周りの星座の星々よりも目立つ土星が見えています。1月3日から5日にかけて、細い月が金星と土星に相次いで接近して見られます。
3日は、月が金星のやや下側に位置します。4日には、月が金星と土星の間に入り、明るい3つの天体がほどよく並んで印象的な光景となりそうです。
5日になると、月は土星の上側へと移動します。3日間続けて観察すると、金星や土星とくらべて月の移動量が大きいことが実感できます。それぞれ明るい天体ですので、毎日同じ時間に写真撮影をするなど記録をとって比較してみると、位置関係の変化がよりわかりやすくなるでしょう。
好条件のしぶんぎ座流星群を観察しよう!
しぶんぎ座流星群は、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群とともに三大流星群と呼ばれています。ただし、毎年安定して多くの流星が出現するペルセウス座流星群やふたご座流星群と比べると、しぶんぎ座流星群は、活動 が活発な期間が短いことや、年によって出現数が変化しやすいことから、流星が多く見える年は限られます。
今年のしぶんぎ座流星群の極大は、1月4日0時頃(3日深夜)と予想されています。ただしこの時間帯は、日本では放射点が空のたいへん低い位置にある(または昇っていない)ため、流星が出現したとしてもその数はとても少なくなります。その数時間後にあたる4日未明から明け方の時間帯には、放射点も高くなり見ごろとなるでしょう。月明かりの影響もなく、好条件のもとで観察できそうです。
流星が目立って見え始めるのは、4日2時頃です(時刻や流星の見え方は東京付近の場合。以下同じ)。時間の経過とともに放射点が高くなり、流星数が増加していきます。最も多く見えるのは5時頃で、実際に見える流星の数は、空の暗い場所で1時間あたり約30個と予想されます。その後は夜明けとともに、流星も見えなくなります。
流星は、放射点を中心に放射状に出現します。
ただし、放射点付近だけでなく、空全体に現れます。いつどこに出現するかも分かりませんので、なるべく空の広い範囲を見渡すようにしましょう。また、屋外の暗さに目が慣れるまで、最低でも15分ほどは観察を続けると良いでしょう。レジャーシートを敷いて地面に寝転んだり、背もたれが傾けられるイスに座ったりすると、楽な姿勢で観察できます。たいへん寒い季節ですので、寒さ対策をしっかりおこなってください。事故に遭わないように十分注意し、マナーを守って観察をしてください。
(※国立天文台の記事を一部転載しております)